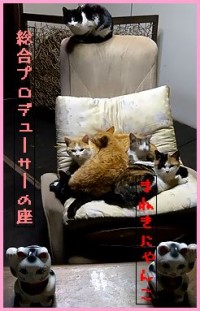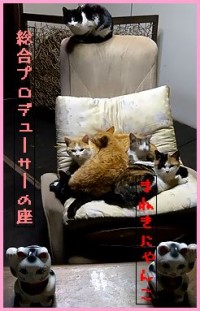ダンスがブームである。
「地元の東御市文化会館でダンスの発表会はできないかしら」
一人のママさんがそう言った。市内のヒップホップダンス教室で幼い我が子とダンスを楽しむ若い婦人だった。若い地元のダンサーと一緒に、数人からはじめたママさんたちの教室は瞬く間に数十人が集まる大所帯に育ったと聞いた。
ボクは流行には甚だうといけれど、フラ(フラダンス)やフラメンコに熱中するご婦人の姿をよく見かけた。ご老人が通う公民館の健康教室でもあれは体操というよりは踊りであって、演歌にあわせて肩や背筋を伸ばしているのだった。
ママたちは言う。「子供たちの野球やサッカーなどスポーツ大会はあるけれど、ダンス大会はこの地にはない。イベント会場に招かれて踊るがせいぜいであるぐらいです。踊る機会が欲しくて出演するけれど、主催者にすれば客寄せのアトラクションの扱いだから、衣装の着替えする場所すらない。一度、是非、子供たちの姿を見て欲しい」と、誘われた。
昔、駅前で踊る若者に話を聞いたことがある。「何故に君らはズボンを下げパンツ見せるようなだらしない風体で踊るのか?それも人通りの激しい駅前の歩道でだ」…..オヤジの高飛車な問いかけは無礼なものだったに違いない。「帽子というものはひさしを前にかぶるものだ。なぜフードで顔を隠した上に横向きにかぶるか?みっともない!浮かれてないで勉強しろ!それがお前たちの本分じゃないか」…ガチガチと凝り固まった感性だろうが、これが本音だった。高校生だというその若者は言った。「仲間と待ち合わせするには駅前がいい」。誰か他の仲間も来るかもしれない…と彼は言った。ロッキング、とかいう楽しいフリまで教えてもらった。気のいい爽やかな若子だった。ショーウィンドウのミラー越しに、行き過ぎる人波が流れた。
人が集うところダンスあり….楽しいからダンスなんだ….ダンスは人を招く…ダンスは力を持っている、ダンスはいい。地元東御市文化会館でダンスの祭典を開こうか。
誰にも覚えがある学芸発表会ではない、一流の芸術公演をいくつも披露してきた756席収容の檜舞台での本格公演…企画を詰めた。自宅や学校や体育館や公民館や、あるいは街角の通りや広場で踊る巷のダンサーを、ジャンルを問わずに舞台にあげる。老いも若きも幼きも、無論ハンディのあるなしもなく、無制限に出演者を募る。巷(ちまた)のいわば名も無き趣味のダンサーを一個の個性的なるアーティストとして扱う…ボクらはこれを基本に据えた。
開館から20年を迎えた町の文化会館が主催する記念事業の枠から薄い予算を取り付け、市民公募によるボランティア実行委員会で自主運営する企画をあげた。「我が子のダンス発表交流の場が欲しい」と願う市内のダンス教室のメンバーが実行委員に名乗りをあげた。手弁当、ダンスにひたむきな情熱を傾ける子供たちとその母親だ。公営の大きな文化施設をリハーサルを含め数日間押さえ、照明、音響やらの舞台設備をフルに使う。文化会館運営が指定管理制度導入に伴い民間の手に運営の一部が移ったことで可能となった文字通り市民主導…行政の言葉でこれをくくれば、「市民主導の行政との協働によるダンスフェスタ」ということだ。
フェスタ運営の成否は、この実行委員会の肩にかかっていた。素人の公募市民の情熱で、これが可能となるなら、これほど新鮮で痛快なことはないと思った。運営事務局を行政庁内に設け職員がこまごまと準備をすすめるしかなかったこれまでの行政主導による市民参加ではない。行政は指定管理制度を通じてこれを見守りサポートするだけ。舞台の主役も市民なら、企画から運営一切も市民の手による。これは自ずと「自主自律」の責任をダンサー個々にも問うものだった。
総合プロデューサーを引き受ける際、私は実行委員に念を押した。「フェスタを皆さんは本当にしたいのですね」と、本気の度合をボクは計りたかった。出演者公募、折衝、スケジュール調整、スポンサー募集、広報、公演会場運営、ほか山とある準備の雑務を一手に引き受け、忙しさに本番当日の我が子の舞台さえ見れないかもしれない。硬固で柔軟な組織が必要だった。
主催者となった東御市文化会館は、出演者の企画演出要望を全面的に受ける姿勢で、「舞台技術体験型」を採り、舞台を開放した。市文化会館主催事業としての補助金のみでフェスタ事業がまかなえるはずもなく、多くの事業者や企業の皆様から大きな協賛を得ながらの開催となった。
▽第1回ダンスフェスタ 平成22年11月21日 (収容756席) 出演者総数250人、入場者数650人 ▽第2回ダンスフェスタ 平成24年2月19日 出演者総数約400人、入場者数1000人
多くの方々の大きな協力のもと、ともにうみだすみらい、とうみダンスフェスタは、まずは成功したと思う一方、会場を埋めるたくさんの観客を眺めつつもなお、これで終わりとはボクらは考えない。裏方として、安全第一に無事終えたことへの安堵感があるだけだった。イベントは予想の付かないことが多々起きるのが常….運営上のミスも表面化し、完璧だったなどとは言えるわけもない。ダンスフェスタの継続に緻密な企画の精査が必要だろう。
公演を前に忙しく刷った会場向けのプログラムの校正ミスから、主催者を東御市文化会館とするべき所を文化会館の文字が抜けて東御市となった。訂正をかけはしたものの、来賓席の市長から直接、強く注意受けた。東御市主催と東御市文化会館主催の違いは、実行委員会のキッズやママさんにとって別にどうでもよい話だ。ともにうみだすみらい東御のフレーズの下、わがふるさとへの思いがあるだけだった。しかし、東御市主催となると市長は来賓席の人ではなくなる。事業自体の本質が変わる。あってはならないミスだった。主催者の文化会館には運営責任者であるボクの辞任の意を添えて謝罪した。翌日には文化会館の館長が経緯を説明し「間違いは間違い」として市長室に出向いて謝罪した。当然とるべき公施設の厳格さだ。ボクらは表には出ない黒子である。しかしダンスフェスタ開催の責任者であることは、市長自らが会場で公にしてくれた。責任をとるべきはボクだった。
実行委員会の皆様の中にも「実行委員会はほんとうに必要?」と運営のあり方に疑問を投げる声もあると聞いた。
時流に乗ったというわけではないが、ダンスフェスタの運営総括を務めた。踊りといえば、幼い頃の盆踊りと、高校時代のフォークダンス、インドシナのキャバレーでガラス越しに招く綺麗な金魚姫と一緒に揺れた記憶….いづれにせよ、人前で自慢できるダンスはない。
今回の第2回開催を機にボクは総括責任の任を降りる。別のステージで我流のステップを踏もうと思う。心は未だロッキング……ダンスフェスタ実行委員会の皆様、お後はよろしいか?